良い演奏には「曲の解釈」ということが欠かせないと以前書きました。ある曲を深く正しく理解したり、作曲家の本当の意図を知ったり、もしそれがわからなければ想像力を働かせたりすることも大事ですが、そういうことに大いに関係していると思うのがやはり一つは読書だと言えます。
今の時代は本ではなくても情報はいろいろ取れると思う人がいるかもしれませんが、それでもやはり読書からしか得られないものがあると感じます。音楽の勉強においては、例えば作曲家について知ろうと思えば、一般的な知識や教養であればチャットGPTが答えてくれるかもしれませんが、少し専門的なことや正確性が求められる事物については本でしかわからないこともまだ非常に多いと思います。もうその人がどれだけの本を読んでいるかということにかかっています。
良い読書をしていると、例えば作曲家が考えていたであろうことや、歴史的あるいは文化的な背景、また作曲家個人にまつわる人間関係や心の動きなどについて思いを巡らせたり、そこから興味を持ってさらに学ぶ範囲を広げていったりする過程で、やはり物事への深い共感とか理解ができるようになっていきます。これがもちろん音楽性を高めることにも繋がります。
また、逆に知識などが足りないためにある曲に十分に自信のある解釈を与えることができない、ということもあり得ます。例えば和声法を知らなかったり、それ以外にも音楽の基礎的な仕組みや専門用語を知らないとか、音楽史的な視点から考える力に欠けるとか、音楽そのものを理解するためのその他の教養が足りなかったりします。例えば音大ではある程度の基礎はもちろん授業等でひととおり学べますが、自分で独学して求めなければ決してわからない事柄も無限に出てきます。だからこそ、学べば学ぶほど演奏にも深みが出てくるということがあり得ます。
だから学生の時代から読めるものはどんどん勉強して、その後も読書はずっとずっと続けていくべきだと思います。ただ、多くの場合は演奏を磨き続けるために必要な「練習時間」を確保することのほうがより重要だと思われ、特に演奏家を目指す人には他のことをする時間がなくなっていくのです。とにかく空いた時間があればそれは練習に充てる、という考え方が正しく思えてしまい、実際に演奏家はそれほど忙しいケースが多いですし、もし名前が売れて活動が増えてくればさらに時間がなくなるので本を読む時間はもっと少なくなっていく、ということになるのでしょう。
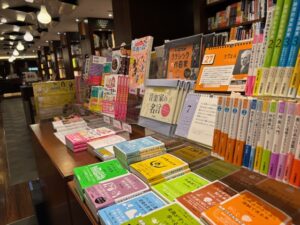
以前ペルージャ音楽祭でご一緒したピアニストにスティーブン・スプーナーさんという方がいらっしゃるのですが、彼はなんと今年フランツ・リストの10巻セットのCDの録音を出したのですが、その後のインタビューをいくつか聞いて感銘を受けました。とにかく音楽への入り込み方がすごいのと、彼の話を聞いていると(もちろん演奏もですが)リストにこれほどの魅力がまだ隠されていたのか!と思わされました。彼は素晴らしいピアニストなのですが同時に勉強家でもあり、特にコロナ禍で時間がたっぷりあった時には、アラン・ウォーカーの著作などありとあらゆるフランツ・リストに関する本を片っ端から読み返したということです。話を聞いていると本当に作曲家リストについての思索が深く、あらゆる知識に彩られていて話が面白く、そして人の心を打つほどの音楽への深い共感と入れ込み方を感じました。
忙しいと本を読む時間をどのように捻出するかというのは大きな問題ですが、それを続けていくことの重要性を若い人たちにもぜひ強く感じてほしいと思うこの頃です。本を読むための空間と時間の確保が何よりも大切だと思われますし、ぜひピアノを勉強している人たちもそのことに思いを向けてほしいものです。音大の図書館をはじめ、地域の図書館などもぜひもっと利用して貪欲に本を読み続けていってほしいと思っています。
