「別れの曲」で有名なこのエチュードですが、弾きやすそうなので皆さん挑戦してみたくなるでしょう。ただ、途中からちょっとだけ難しくなりますね。
私のところに熱心な大人の生徒さんが通ってきています。彼は、驚くべきことに、毎回のレッスン時に楽譜を10〜20冊くらいカバンに入れて持参して来ます。例えばショパンのエチュードをやっている時は、その持参楽譜の半分は「ショパンのエチュード集」です。(彼はあらゆる版を買って持ち歩いているのです!)
先日、「別れの曲」の38-40小節あたりの指使いについて質問されたのですが、ここは確かに迷う箇所かもしれませんね。私自身は「これ」と決めてある指使いがあるのでそれを教えましたが、コルトー版では参考として9種類くらい書いてあります。そして、質問した彼が弾いていた指使いのように、コルトーの挙げたもの以外にも妥当な指使いはいくつか考えられます。
ただ、「指の自然さ」と「音の響きの良さ」を考えると、自分にとっての理想的な指使いというのは1〜2種類に絞られてくるでしょう。私などは、ショパンのエチュードは全曲、ほぼすべての音において自分の理想とする指使いが決まっていますが、多くの他のピアニストもきっとそうおっしゃることでしょう。
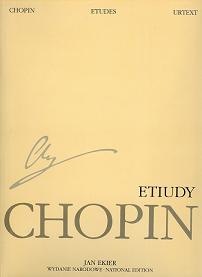 ところで、最も新しい研究による成果とされるナショナル・エディション(エキエル版)では、この曲の31小節と34小節目が従来の版と違うものになっているのは知られていると思います。こちらのほうがよりオーセンティックであるとして、耳慣れないハーモニーに変更されているのですが、でも演奏会でこの通りに弾くのはやはり勇気が要りますよね。この曲に耳馴染みの人は、「この演奏家、読譜が間違っているんじゃない?」と思うでしょうから。ショパンコンクール審査委員長氏も「エキエル版は素晴らしいが、音の変更だけは私はついていけない。マズルカなど、もう50年以上も弾き続けてきた愛着のある音を今さら変えられない」と言っていましたね。
ところで、最も新しい研究による成果とされるナショナル・エディション(エキエル版)では、この曲の31小節と34小節目が従来の版と違うものになっているのは知られていると思います。こちらのほうがよりオーセンティックであるとして、耳慣れないハーモニーに変更されているのですが、でも演奏会でこの通りに弾くのはやはり勇気が要りますよね。この曲に耳馴染みの人は、「この演奏家、読譜が間違っているんじゃない?」と思うでしょうから。ショパンコンクール審査委員長氏も「エキエル版は素晴らしいが、音の変更だけは私はついていけない。マズルカなど、もう50年以上も弾き続けてきた愛着のある音を今さら変えられない」と言っていましたね。
でも、もし果敢な演奏者がたくさん現れたら、クラシック音楽もなんだか流動的な感じがして楽しいですよね。「この音しかない」と堅苦しく決めつけられるよりも、客観的に見たらそのほうが自然に見えるかもしれません。クラシック音楽を演奏する場合は、一般的には勝手に作曲や編曲をしてはいけませんから、せめて解釈については大幅に許されるようになってくると良いですね。